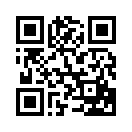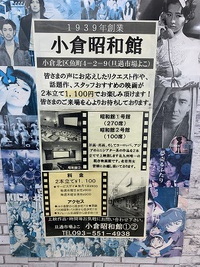2018年11月01日
石神様(その23~大岩屋)
今日、11月1日は「イイ単気筒の日」
愛車はヤマハだけど、バイクはホンダが一番と思っている。
単気筒は1990年代の空冷XR系が至高
で、本題
トカラ列島の小宝島にある、平家の落人が隠れ住んだ
(と言い伝えられている)大岩屋
隆起サンゴ礁の島の小宝島にどうやって洞窟が
出来たのかは不明

溶岩が固まる時に火山性ガスが抜けた穴ではない、と思う。
画像で分かるように地層の中にある洞窟
天井は緩やかな弧をかいているが地面は平たん
水による浸食作用にしても島内に河川、つか水源はないし
波による浸食にしても洞窟の形状になるのは不自然
(沖永良部島や与論島と違って)内部には鍾乳洞とかは無い。
不思議な場所
大岩屋の案内板には
~(省略)~
中央部には赤ちゃんを寝かせた「イサ」と呼ばれるゆりかごを
吊った穴が天井に2対(計4か所)空いています。
なお、この大岩屋には太平洋戦争末期(昭和20年5月)に
米軍の空襲を受け、島民の半数が焼け出された際、約4か月間、
2世帯16名が避難生活を送った記録が残されています。
~(省略)~
と書かれている。
防空壕(のようなもの)は「うね神」にもあったらしい。


大岩屋の前には風よけ、目隠しのように化石サンゴの
石垣があり、塊状&板状サンゴ混合の形状だった。
これらの化石サンゴをどこから掘り出してきたのかは不明
山の中を探せば採石場のような場所が見つかったのかも
知れないが、その日は暑かったのと、地元の爺様に
「不注意に草むらの中に入るとハブ(トカラハブ)に噛まれるぞ」
と脅され、山には行かなかった。
今思えば、そう言うことで部外者を禁足地から
遠ざけていたのかも知れない。
大岩屋(洞窟)は、男根型の陽石の対局にあるような存在。
岩の割れ目がどことなく女性性器をイメージさせ、
洞窟内に入ることで子宮内部にいるような感覚に陥らせる。
ある意味、パワースポットだった。
だとすれば、入口が石垣で隠されているのも当然、
女性性器だもの。
石垣の積み重ね方に特徴があるような、ないような。
私がそれを知らないだけで、サンゴの石垣には「喜界島流」、
「笠利流」、「加計呂麻流」などといった、
(使用するサンゴの形状と積み重ね技法で)
それぞれ特色のある建築様式があるのかも知れない。
愛車はヤマハだけど、バイクはホンダが一番と思っている。
単気筒は1990年代の空冷XR系が至高
で、本題
トカラ列島の小宝島にある、平家の落人が隠れ住んだ
(と言い伝えられている)大岩屋
隆起サンゴ礁の島の小宝島にどうやって洞窟が
出来たのかは不明

溶岩が固まる時に火山性ガスが抜けた穴ではない、と思う。
画像で分かるように地層の中にある洞窟
天井は緩やかな弧をかいているが地面は平たん
水による浸食作用にしても島内に河川、つか水源はないし
波による浸食にしても洞窟の形状になるのは不自然
(沖永良部島や与論島と違って)内部には鍾乳洞とかは無い。
不思議な場所
大岩屋の案内板には
~(省略)~
中央部には赤ちゃんを寝かせた「イサ」と呼ばれるゆりかごを
吊った穴が天井に2対(計4か所)空いています。
なお、この大岩屋には太平洋戦争末期(昭和20年5月)に
米軍の空襲を受け、島民の半数が焼け出された際、約4か月間、
2世帯16名が避難生活を送った記録が残されています。
~(省略)~
と書かれている。
防空壕(のようなもの)は「うね神」にもあったらしい。


大岩屋の前には風よけ、目隠しのように化石サンゴの
石垣があり、塊状&板状サンゴ混合の形状だった。
これらの化石サンゴをどこから掘り出してきたのかは不明
山の中を探せば採石場のような場所が見つかったのかも
知れないが、その日は暑かったのと、地元の爺様に
「不注意に草むらの中に入るとハブ(トカラハブ)に噛まれるぞ」
と脅され、山には行かなかった。
今思えば、そう言うことで部外者を禁足地から
遠ざけていたのかも知れない。
大岩屋(洞窟)は、男根型の陽石の対局にあるような存在。
岩の割れ目がどことなく女性性器をイメージさせ、
洞窟内に入ることで子宮内部にいるような感覚に陥らせる。
ある意味、パワースポットだった。
だとすれば、入口が石垣で隠されているのも当然、
女性性器だもの。
石垣の積み重ね方に特徴があるような、ないような。
私がそれを知らないだけで、サンゴの石垣には「喜界島流」、
「笠利流」、「加計呂麻流」などといった、
(使用するサンゴの形状と積み重ね技法で)
それぞれ特色のある建築様式があるのかも知れない。
Posted by XYZ郎 at 22:50
│トカラ列島